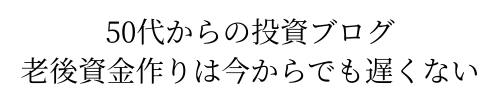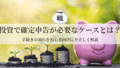株式や投資信託の配当を受け取ると、所得税や住民税が課税されますが、「配当控除」という制度を活用することで税負担を軽減できる場合があります。
この記事では、配当控除の仕組みや適用条件、税金対策としての活用方法を初心者にもわかりやすく解説します。
1. 配当控除とは?
配当控除は、株式の配当金にかかる所得税・住民税の一部を控除できる制度です。
これにより、二重課税の負担を軽減し、配当所得の実質的な税率を下げる効果があります。
配当金は会社の利益から法人税が支払われた後に分配されるため、配当金受取時にも所得税が課される「二重課税」が問題となります。
配当控除はこの問題を緩和する目的で設けられています。
2. 配当控除の仕組みと計算方法
配当控除は、確定申告の際に配当所得に対して一定割合の控除が適用されます。
控除率は所得税と住民税で異なり、おおよその計算は次の通りです。
- 所得税の配当控除:配当所得の10%(課税所得1,000万円以下の場合)
- 住民税の配当控除:配当所得の2.8%
例えば、年間10万円の配当所得があった場合、所得税から約1万円、住民税から約2,800円が控除され、実質的な税負担が軽減されます。
3. 配当控除を受けるための条件
- 配当所得があること(株式や投資信託の配当金など)
- 確定申告で「申告分離課税」ではなく「総合課税」を選択すること(※)
- 国内株式や国内投資信託の配当金が対象
※通常、配当は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、自動的に源泉徴収され確定申告不要となるため、配当控除を受けるには自分で確定申告し「総合課税」を選ぶ必要があります。
4. 配当控除の税金対策としての活用法
- 確定申告で総合課税を選択する
源泉徴収されている場合でも、申告分離課税から総合課税に変更し配当控除を適用すると税負担が減ることがあります。 - 所得控除や税額控除と組み合わせる
医療費控除や住宅ローン控除など他の控除と併用することでさらに節税可能です。 - 配当再投資型の投資信託やNISAの活用
配当控除の対象外でも、非課税制度を活用することで税負担を抑えられます。
5. 配当控除利用時の注意点
- 配当控除を受けるためには確定申告が必要で、手続きが煩雑になる場合がある
- 配当控除の適用により所得税率が変わることもあるため、総合課税を選ぶと逆に税負担が増えるケースもある
- 外国株の配当や海外投資信託の分配金は対象外
まとめ|配当控除を理解して賢く節税しよう
配当控除は、国内株式や投資信託の配当所得にかかる税金を軽減する重要な制度です。
ただし利用には確定申告が必要で、状況によっては節税効果が薄い場合もあります。
自身の投資スタイルや所得状況を踏まえて、申告方法を選択しましょう。
また、NISAやつみたてNISAなどの非課税制度とも組み合わせることで、より効率的な税金対策が可能です。
賢く税金を抑え、長期的な資産形成に役立ててください。